下西風澄トークイベント
はじまりの哲学 〜制御する心から、上演する心へ〜 Vol.2
Event Date : 2018.2.9


「人工知能は突如として来襲してきた技術ではなく、西洋の内側で数千年の
時間をかけて構築されてきた思想であり、それを結実するために生まれた技術。」
後編は、哲学者の下西風澄さんが古代・近代、東・西と自在に行き来しながら、
思想の歴史と私たちが向き合う未来について案内します。


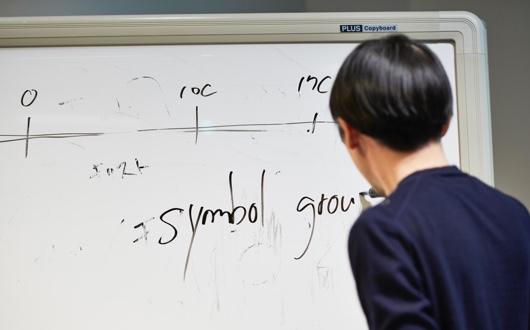
行為の循環によって心が生まれる
行為の循環によって心が生まれる
下西
ソクラテスの時代からだいぶ飛んで17世紀のフランス。ルネ・デカルトという哲学者が登場します。彼はソクラテスの考えから飛躍した興味深い主張をしました。「この世界には二つの存在しかない。心と物である」と。精神と物質ですね。ソクラテスにとって肉体は精神が宿る場所なんですが、デカルト的には肉体は単なる「物」で、機械と一緒です。この考え方の延長線上に生まれる考えが1950年代の認知科学ですね。また、人工知能の研究だけなく、脳科学の発展とも結びついて、脳こそが世界を認識する心であり、それは機械によって再現できる、という発想が強固なものになりました。
そんなデカルトの主張に真っ向から対立する主張をしたのが、フランシスコ・ヴァレラという神経生物学者・思想家です。僕は大学院で主にこの人の研究をしていました。ヴァレラは1973 年のチリで起こった軍事クーデターによって亡命を余儀なくされた学者なんですが、彼は亡命先のアメリカ・コロラド州で仏教や禅の思想に出会います。実は1960〜1970 年代のアメリカは、ビートニクやカウンターカルチャーと結びついて仏教思想が一気に広がり始めた時期でもありました。その中心のひとつがコロラドにあるナローパ・インスティテュートなんですが、これが後にアメリカ初の仏教大学になります。ヴァレラはそこで仏教者たちと出会い、彼らの思想に触れるうちに、心についての新しい概念を考えるようになるんですね。彼は、脳と心は別の物であって、いくら脳のことを調べても心のことはわからない、と直観した。だから、多くの脳科学者たちが、脳から心を理解しようとしていたなか、むしろ心の側から脳を理解しようとしたんです。そして、心というのは脳単体で存在するわけではなく、身体があることではじめて成立するのではないかと主張し、それを「身体化された心」と呼びました。

下西 風澄
哲学者
下西 風澄。1986年生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学後、哲学を中心に執筆活動を行う。主な論文・執筆に「フッサールの表象概念の多様性と機能」(『現象学年報 第33号』)、「色彩のゲーテ」(『ちくま』2014年8-10月号)、「詩編:風さえ私をよけるのに」(『GATEWAY 2016 01』)など。連載に「文学のなかの生命」(『みんなのミシマガジン』)、「夕暮れのサイエンス」(『GINZA』)。近刊に絵本『10才のころ、ぼくは考えた。』(福音館書店)。
kazeto.jp
下西
「一杯の紅茶はハエにとっては広大な海だが象にとっては気がつかないほどの小さな水の粒に過ぎない。知覚されるものは有機体の生の形式と行為と不可分な形で現れる。行為によって私たちは世界をその都度作る」
少し難しいですが、「有機体の生の形式」というのは、生物の身体的構造と知覚形式のことです。ヴァレラは、身体をもった主体が、行為によって外側の環境と相互作用することによって、ふたたび自分自身の行為を変えていくという循環プロセスこそが、人間の知覚や心の本性なのではないか、と考えたのです。彼はこれを「Enactive Mind」と呼びました。「Enact」という語は、「行動」や「(法などが)成立する」という意味の言葉です。「行為から産出された心」と訳されることが多いのですが、僕は「上演する心」と訳してみたいと思っています。今日のもうひとつのタイトルですね。
Enactという言葉には「(劇を)上演する」という意味もあるんです。最初は何もない舞台に役者や舞台装置が揃い、それらが動くことで上演が成立する。それまで何もなかった場に、行為が生じることで、その束の間、演ずる主体と演じられた世界が同時に成立する。そして劇が終われば、それはたちまち立ち消えてしまう。僕たちは、確固とした世界に存在している情報を一方的に受け取って認識するのではなく、自分が世界に働きかけるまさにその行為によって、世界を絶えず生成している。「私」が「行為」するのではなく、「行為」が「私」を創造する。それが、認知や心の本質だと思うんです。
ヴァレラが注目した“縁起”
ヴァレラが注目した“縁起”
下西
ソクラテス、ホッブズ、デカルト…認知科学や心の概念のベースとなっていたのは西洋の哲学です。しかし、ヴァレラはこれら西洋哲学に基づいて心の問題を考えることに限界を感じた。そこで東洋の考え方に目を向けます。なかでも彼が注目したのが「縁起」という思想です。縁起はもともとサンスクリット語で「pratītya-samutpāda」、英語では「Co-dependent arising」と翻訳されるんですが、これは「共に依存しながら生じる」という意味です。いい翻訳ですね。心はそれだけで自己の主人になる存在ではなく、他者や環境とインタラクションしながら生成していくという考え方です。
ソクラテス以前の時代は世界が不安定で何に頼ったらよいのかわからない時期でした。そうした時に自分自身を律するしっかりとした主体、大地がほしい。ソクラテスは、あまりに混沌とした不安定な世界のなかで、安定した世界認識を獲得するために、「自己」というひとつの基盤を発明して心の中心に据えた。そういう精神が西洋哲学の起源であり基本です。しかし東洋の伝統では、すべてのものが依存し合って生じているという考え方を基本にしています。世界はそもそも網の目のように張り巡らされたネットワークであって、すべての存在が互いに依存しあいながら生成と消滅を繰り返し続けている。安定した自己や世界などあり得ず、万物流転の不安定な世界を受け入れつつ生きようという精神です。これは西洋世界から見たら斬新な発想で、多くの西洋哲学者たちも魅了されてきました。最後にこれらのことを踏まえつつ、日本に目を向けてみましょう。



心と身体の狭間で悩んだ夏目漱石
心と身体の狭間で悩んだ夏目漱石
下西
心について考えてきましたが、この問題に向き合うにあたって重要な日本人がいます。夏目漱石です。明治維新が起きて日本が一気に近代化を迎えていく時代に活動した作家ですね。1853年にペリーが来航して、1868年が明治元年なので、わずか15年のうちに、幕藩体制から近代的社会制度へと以降していった激動の時代です。この時期は政治体制や行政制度も大きく変わるのですが、同時に人間の意識も変わっていった。漱石は、そんな過渡期に心と向き合い、そして苦悩した人物です。
初期の漱石は東洋的な理想を持っていた人で、それによって結実させた表現はヴァレラが目指したものに近かったのではないかと僕は思っています。例えば、青年が山に登って漢詩を書き、絵を描こうとする物語『草枕』という初期の作品があるのですが、その中で彼はこう綴っています。
「あらゆる春の色、春の風、春の物、春の声を打つて、固めて、仙丹に練り上げて、それを蓬莱の霊液に溶いて、桃源の日で蒸発せしめた精気が、知らぬ間に毛孔から染み込んで、心が知覚せぬうちに飽和されて仕舞つたと云ひたい。」
−夏目漱石『草枕』
春の景色に包まれているうちに、自分が「春そのもの」になってしまう。春の色、春の風、春の物、春の声…あらゆる春が自分の身体に染み込み、その境界が曖昧になる境地。自己の内面と外側の環境の区別がなくなり、周囲とのインタラクションの中で新しい自分を立ち上げていくという感覚。まさに「上演する心」です。
ただ、残念ながら漱石はこの思想を貫けませんでした。晩年の後期三部作と呼ばれる作品の中のひとつ『彼岸過迄』の一節です。
「市蔵という男は世の中と接触する度に内へとぐろを巻き込む性質である。だから一つ刺戟を受けると、その刺戟がそれからそれへと廻転して、段々深く細かく心の奥に喰い込んで行く。そうして何処まで喰い込んで行っても際限を知らない同じ作用が連続して、彼を苦しめる。仕舞にはどうかしてこの内面の活動から逃れたいと祈る位に気を悩ますのだけれども、自分の力では如何ともすべからざる呪いの如くに引っ張られて行く。そうして何時かこの努力の為に斃(たお)れなければならない、たった一人で斃れなければならないという怖れを抱くようになる。そうして気狂の様に疲れる。これが市蔵の命根に横たわる一大不幸である。」
−夏目漱石『彼岸過迄』
初期の漱石は、春と一体化する心、「私」と「春」の境界が消滅した心、つまり上演する心を描いていたのですが、だんだんと西洋からインストールされた個人主義の思想に巻き込まれてしまうんです。自分の中で心が独立して「内面」に縛られる。心が外部と溶け合うどころか、もはや環境にアクセスすることさえできず、自分だけで堂々巡りをする刺激に晒された結果、死について意識するようになる。その悩みは、続く『行人』という作品でさらに深まり、そして「K」が自死する有名な『こゝろ』に繋がっていく。『草枕』で「上演する心/身体化された心」について書いた漱石が、最終的に『こゝろ』という、まるで心が単独で存在するかのようなタイトルの作品を残したのはどこか示唆的ですよね。彼は身体と精神、ハードウェアとソフトウェアの葛藤のなかで悩み、そしてそれを克服できなかったのだと思う。僕は漱石が抱えていたこの問題をどう考えるか、ということに強い関心があります。そしてそれは、現代の心や生き方を考えるためにも重要な視点だと思っています。そういう意味では、僕たちは未だに明治の精神的改革という荒波が起こした矛盾から、つまり漱石の葛藤から、抜け出せていない。
新しい心のあり方について考え続ける
新しい心のあり方について考え続ける
下西
最初に、人工知能は「技術」ではなく「思想」である、と言いました。もしこの考えが正しいのであれば、人工知能に何ができるか、人間にどこまで近いのか、というような議論は本質的ではないと僕は思います。「人工知能」と「人間」という対立があるのではなく、今日お話してきた「制御する心」と「上演する心」という対比がある。結局のところ、問題は人工知能が人間に取って替わるかどうかといったことではなく、僕たちがどういう心のあり方を求めているか、ということが重要なのではないでしょうか。なぜなら人工知能は突如としてどこかから来襲してきた技術ではなく、西洋の内側で数千年の時間をかけて構築されてきた思想であり、それを結実するために生まれた技術だからです。その起源にいたソクラテスが仮に「心を発明」したのだとしたら、まったく別の「心」も僕たちは持ち得たはずです。「ソクラテス的な心=制御する心」というのは、必ずしも人間に与えられた唯一の心の有り様ではなく、いくつもある心のモデルケースの一つかもしれない。だからこそ、僕たちはいま、どういう心を再発明したいのか、そのことを考えることが大事だと思うのです。
ヴァレラは西洋の考え方だけで心を理解することに限界を感じ、東洋の心の捉え方をそこに組み込もうとしました。漱石はその逆で、東洋の自然環境や文化をベースにした精神に西洋の思想をインストールしようとした。結局漱石はそれが上手くできなかったわけですが…それを克服するのは容易ではありません。なぜなら、文明開化や近代化を経験した僕たちにも、既に西洋的な「制御する心」がインストールされているからです。これを単純に排除して逃れることはできない。僕たちにできることは、いまある技術や思想の歴史から、その起源と未来を感じ取り、そのうえでどのような心を創造していきたいのか、生命や身体という条件といかに向き合っていくのか、そしてどう生きていけばいいのか、このことを考えていくことだと思います。なぜなら、技術の背後にある思想と歴史を考えない限り、いくら技術が進歩しても歴史を反復するだけだからです。大切なことは、すでにある「心」のイメージを応用することではなく、新しい「心」のイメージを持つことだと思うのです。
今日は、そんなことを皆さんと共に考えるきっかけの場になればと思って、お話させて頂きました。



