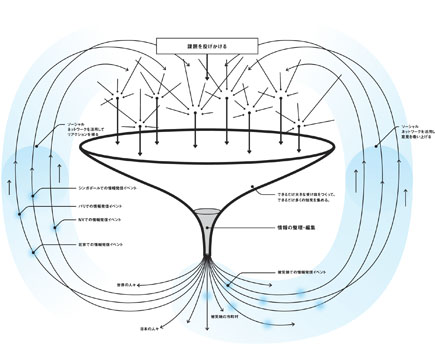列島に目を凝らす

日本列島という国土をどう生かすか。これが日本という国の永遠の課題である。アジアの東の端に、大陸から離れ島々の連なりとして存在する。これは世界の地勢から見てもかなり個性的なことである。
大きな島が4つ。九州、四国、本州、そして北海道。それぞれがほどほどに接近しているので、海底トンネルや巨大橋を架けて、今ではひと続きになった。四つの島には元来「島」という名称はついていない。つまりこの地に住んでいる日本人にとって、これらは「島」ではない。海によって他の世界から隔絶された十分に大きな陸地すなわち「くに」なのである。それ以外の無数の島々には「島」という呼称がきちんと付されている。
隣国との境は海であり、それゆえ境界という観念は明確だ。韓国や中国、ロシアとの間は海。アメリカも太平洋を挟んだ遠いお隣さんである。だから日本には、世界から明瞭に独立しているというイメージが濃厚にある。自ずと「くに」というアイデンティティも強く育まれ、日本語というもう一つの祖国がさらにそのアイデンティティを強固なものへと搗き固めてきた。
一方で、気候風土も独特である。中央アジアのヒマラヤ山脈が8,000m級であるために、偏西風が南に迂回し、湿潤な大気を日本列島上空に運んでくる。これが山々にあたって雨や雪となり、国土の大半を覆うこんもりとした森を生み出すもとになっている。水に恵まれた国土は急峻で、山から海へと毛細血管のように走る川は、大陸の滔々たる大河と比べると流れも速く滝のように俊敏である。火山活動によって出来た大地は変化に富み、温泉がいたるところから湧きだしている。